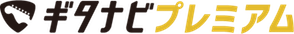- 特集
- ゼロから覚える音楽理論
- 第26回 ツー・ファイブ
ゼロから覚える音楽理論
前回と前々回でドミナントモーションについて解説しました。
ザックリ言うと、ルートの5度上のセブンスコードからルートに解決するコード進行でしたね。
そして、ドミナントモーションにはトライトーンが不可欠だというところまでOKでしょうか。
キー=CであればG7⇒Cこれがドミナントモーションでしたね。
しかし、コード進行の中で唐突にドミナントモーションを使うと「いきなり感」があるのも事実です。
そこで、ワンクッション挟んでスムーズな流れにしようというのがツー・ファイブです。
第26回 ツー・ファイブ
では、ツー・ファイブってそもそも何でツー・ファイブって言うの?という疑問を解消しましょう。
ツーとファイブ、つまり2と5がポイントになってきます。
理論で言う2や5といえば…そう、度数です。
解決したい音に対して2度と5度のコードを使用します。
5度は前に出てきたドミナントの事です。
キー=CでいえばG7にあたります。
では2度、キー=CでいえばDm7になります。
このDm7とG7を使ってCに解決する方法をツー・ファイブと呼びます。
2度と5度を使うからツー・ファイブ。
なんの捻りもない、ズバリそのままです。
では実際の使い方ですが、5度の前に2度を置く、それだけです。
使い方も非常にあっさりですね…
では具体的に例を見てみましょう
 よく見かけるコード進行ですね。
よく見かけるコード進行ですね。
これのG7⇒Cの部分をツー・ファイブにしてみましょう。
Dm7⇒G7⇒Cとすればいいわけですね。
つまりこうなります。
 通称Ⅰ・Ⅵ・Ⅱ・Ⅴ(いちろくにーごー)なんて呼ばれます。
通称Ⅰ・Ⅵ・Ⅱ・Ⅴ(いちろくにーごー)なんて呼ばれます。
(由来は後ほど…)
メロディラインやコード進行に問題がなければ2小節目のAmをDm7に変えてもOKです。
 上記の様に、ダイアトニックコード内で使うとあまり変わった感じがしないかもしれませんが、ツー・ファイブが本領発揮するのは転調や部分転調の場面です。
上記の様に、ダイアトニックコード内で使うとあまり変わった感じがしないかもしれませんが、ツー・ファイブが本領発揮するのは転調や部分転調の場面です。
 例えばこんなコードB♭への進行の場合
例えばこんなコードB♭への進行の場合
B♭をトニックに見立てて、2度のCm、5度のF7を挟みます。
 ツー・ファイブを挟む事で、直接進行するよりスムーズに流れになります。
ツー・ファイブを挟む事で、直接進行するよりスムーズに流れになります。
これは例なので強引なコード進行になっていますが、ツー・ファイブは非常に多く使われています。
前に、セブンスコードを見たらドミナントモーションだと思ってくださいと言いましたが、ドミナントモーションを見たらツー・ファイブかどうかも見てください。
今まで気づかなかっただけで、実はツー・ファイブだった!なんてコード進行もあると思います。
さて、先ほどⅠ・Ⅵ・Ⅱ・Ⅴ(いちろくにーごー)が出てきましたが、ツー・ファイブに続いて数字が続いていますね。
なぜDm7やG7と言わずに2、5、などの数字を使うのでしょうか。
答えは単純に、「キーが変わっても説明できるから」です。
今までこの講座ではCとかAmなどを使ってきました。
それは、なるべく具体的に説明する事で伝わり易いからです。
例えば、コード進行の話をしている時にⅠM7・Ⅵm7・Ⅱm7・Ⅴ7のコード進行で…と書いても分かりづらいですよね。
気楽に読んでもらう為に、なるべく調号を付けず具体的に書いてきました。
しかし、理論書の多くはローマ数字で書かれていることが多いので、この際ちょっと手を出してみましょう。
ローマ数字になると一気に意味が分からなくなっちゃう人は、無理に覚えなくても大丈夫です。
まずは見慣れたキー=Cメジャーのダイアトニックコードです。
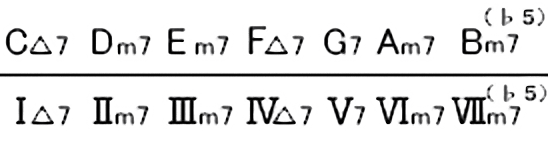
これさえ覚えてしまえば、メジャーダイアトニックは全て同じです。
こちらはFメジャースケールです。
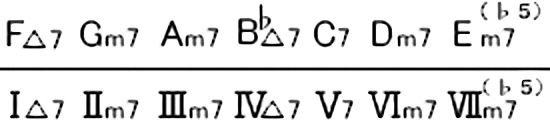 数字で覚えておけばどんなキーでも対応できますよね。
数字で覚えておけばどんなキーでも対応できますよね。
スケールもこれと同じで、ルートとのインターバルがどれくらいかを覚えておけば、ルートの音が変わっても大丈夫です。
ただ、せっかくギターやベースを弾いているので、頭ではなく指板で覚えましょう!
その方が視覚的にも覚え易いですし、指板上を横にずらすだけですからね。
ルートに対してどこが何度になっているのか、スケールやコードを押さえるときにちょっと意識して弾く癖を付けましょう!